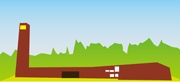【まるで里山が標本箱!巨大昆虫大集合】超高解像度人間大昆虫写真[life-size]
金曜日, 7月 26th, 2024現在、大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ2024が開催中です。
この夏も、キョロロ周辺の里山に人間の大きさまで拡大された超高解像度人間大昆虫写真[life-size]が大集合しています。
大地の芸術祭アーティストの橋本典久氏+scopeが制作する、生物多様性とアートが融合した作品です。まるで里山が標本箱!
トンボの翅の細部やチョウの鱗粉など肉眼では見えない部分もリアルに浮かび上がり、造形の美しさや昆虫の多様性に触れることができる作品です。
この夏はキョロロ周辺に18基の巨大昆虫パネルが設置されています。散策しながら、ぜひ鑑賞してみてください。すべて見つけることができるかな?
超高解像度人間大昆虫写真[Life-size]
https://www.echigo-tsumari.jp/art/artwork/super_high-resolution_human-size_photographslife-size/