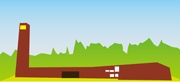【予告】野鳥撮影時における「三脚等の使用」「特定場所での居座り」を禁止します。
金曜日, 7月 5th, 2024【予告】野鳥撮影時における「三脚等の使用」「特定場所での居座り」を禁止とします。
野鳥観察に関するルール・マナー順守をお願いしてきたところでありますが、無断入山・営巣活動への干渉・教育利用への支障が顕著なことから、キョロロの森内における野鳥撮影に関して、以下の行為を近日中に禁止といたします(予告)。野鳥の営巣地保護および教育利用・フィールド管理活動実施のため、ルール・マナーを厳守した野鳥観察にご理解とご協力を改めてお願いします。
・・・・・・・・・・・
<野鳥撮影に関する禁止事項>
〇撮影時の三脚の使用禁止 ※一脚などカメラ固定器具も含む。
〇特定場所での20分以上の居座り禁止 ※椅子の使用を禁止します。
なお引き続き以下のルールをお守りください。
〇無断入山禁止 ※ご利用は開館時間(9時~17時)のみ、休館日の利用はできません。
〇野鳥に必要以上に接近しない。
・・・・・・・・・・・
今年松之山地域内では、カメラマンの営巣地への過干渉により、残念ながらアカショウビンの営巣放棄が発生しています。
第2、第3のこのような悲しい事例を作らないためにも、野鳥観察で訪れる皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
<野鳥観察のルール・マナーについて>
野鳥観察に関するマナーについて、以下のサイト等でわかりやすく・詳しく掲載されています。
・公益財団法人日本野鳥の会 野鳥観察・撮影の初心者の方に向けた、マナーのガイドライン
・公益財団法人日本野鳥の会 野鳥観察マナーについて
・日本野鳥の会大阪支部 野鳥の撮影を考える・撮影時のマナーについて
・千葉県野鳥の会 千葉県野鳥の会の考える野鳥撮影のルール
・Canon 野鳥観察のマナー
※「野鳥観察 マナー」でインターネット検索すると多くの情報があります。ご参考にしてください。