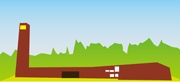【イベント案内】チョウのモニタリング研修会のご案内
日曜日, 8月 18th, 2024里山の草むらや森の中を優雅に飛ぶチョウたち。幼虫が特定の植物に依存して育つチョウは環境の変化を測る物差しとして身近な生き物です。キョロロではこうしたチョウを野外で調べる方法を学ぶ研修会を開催します。講師は日本チョウ類保全協会の中村先生!チョウを通じて自然環境をモニタリングしていく方法について興味がございましたら是非奮ってご参加ください。チョウの観察初心者の方も歓迎です。



日 時:9月8日(日)10:00~12:00
講 師:中村康弘先生(日本チョウ類保全協会)
参加料:無料(別途入館料600円が必要になります)
会 場:キョロロ多目的ホール・キョロロの森
※詳しくはこちらのチラシをご参照ください
※キョロロでは過去の調査イベントでチョウ類の調査をした成果として松之山のチョウ類の図鑑を作成しています。ご興味がございましたら、こちらからPDFファイルをダウンロードして下さい。
注意:キョロロのイベントではなく、日本チョウ類保全協会主催のイベントとなります。以下のemailアドレスまたは電話/FAXにてお申込みください。
email: jbcs@savebutterflies.jp (@を半角にかえてお送りください)
TEL/FAX: 03-3775-7006; 携帯: 080-5127-1696