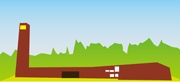2025年3月17日(日)に雪里の冬期の特徴的な虫、雪上に現れる「雪虫」の調査を行いました。毎年冬期に行っている調査ですが、今回はちょっと趣向を変え、参加者と共に実験的な方法で雪虫の生態を調査してみました。
実際に雪虫は降雪があった直後は雪上から姿を消し、降雪が止んでしばらくするといつの間にか雪上現れています。雪から飛び出た樹木などの植物体は降雪時の雪虫の避難場所となっており、雪虫は樹木の幹などの周囲に空いた雪のトンネルを通じて土壌と雪上を行き来していると言われています。実際に雪から飛び出た枝の周りには多くの雪虫を確認できますが、本当に雪虫が土壌と雪上を行き来しているのかは分かっていません。
今年の1月の雪虫しらべでは雪の下にいるクモや昆虫などの小動物を調べた結果、頻繁に雪上で観察できる雪虫は積雪下の土壌中からはほとんど見つけれられませんでした(1月の雪虫しらべのご報告はこちら)。2月の調査では土壌と雪上の間の積雪中にいる可能性を検証するために雪を掘って雪虫を探してみましたが、こちらでも雪中からは雪虫は見つかりませんでした。
今回、3月の雪虫しらべでは視点を変えて雪の下ではなく樹木の幹上にいる雪虫を調べてみました。

【調査方法】
キョロロの裏手のコナラとクリの木に、スギの枯れ葉を10g入れた網袋(リターバッグ)を高さを変えて括り付けました。高さは設置時の雪面を基準として-50cm、0cm、50cm、100cm、150cmの5地点(B~F)、さらに設置した木100cmの距離の雪上に1地点(A)の計6地点。設置から約8時間後の雪虫しらべで各網袋の中に入っている雪虫の種類と個体数をカウントしてみました。

▲設置した網袋(リターバッグ)

▲実験方法の模式図
【結果】
| コナラ | クリ | |
| A | クロユキノミ×4 | クロユキノミ×23 |
| B | サヤツメトビムシ×2
クロユキノミ×2 |
サヤツメトビムシ×1 |
| C | - | |
| D | サヤツメトビムシ×3 | クロナンキングモ×1 |
| E | サヤツメトビムシ×2
ヒメグモ科の一種×1 |
サヤツメトビムシ×1
ケダニ亜目の一種×1 |
| F | サヤツメトビムシ×2 | サヤツメトビムシ×3 |
※コナラの網袋B、Cは採集時にサンプルが混合したため同一のものとしてカウント
雪虫の代表格であるクロユキノミは雪上に設置した網袋(A)からは数多く見つかったのの対し、各樹木の幹に設置した網袋(B~F)からはクロユキノミはほとんど見つけられませんでした。一方でクロユキノミほど頻繁には見つからないものの、やはり冬期を通じて雪上で見つかるサヤツメトビムシは各樹木の幹に設置した網袋からしか見つけられず、しかも設置した網袋の高さとその中のサヤツメトビムシの個体数に関連性は無い様でした。
今回の結果から考えるとクロユキノミは雪上に現れると樹木を通じて垂直移動することはあまり無いのかもしれません。しかしながら野外観察ではクロユキノミが雪から飛び出た枝の周りにいる光景はよく目にします。仮にクロユキノミが垂直移動をあまりしないのであれば、こうした行動は降雪で埋まることを避けるための一時的な退避場所として樹木の枝を利用しているだけで、飛び出ている枝の方向(つまり穴の方向)や時期、積雪深等によって枝の周りのクロユキノミの数は変化するのかもしれません。

クロユキノミ(トビムシ目ツチトビムシ科)
またサヤツメトビムシは雪上から見つかることがあるものの、今回の結果からはその生息場所は主に樹木の幹上であることが分かりました。また、雪面からの高さに依存せずに幹上に分布していることも示唆されました。どれくらいの高さまでいるのか、あるいは逆に雪面からどれくらいの深さまで分布しているのか興味があるところです。

▲サヤツメトビムシ(トビムシ目ツチトビムシ科)
今回の調査ではトビムシの仲間の他にヒメグモ科の一種やクロナンキングモ(サラグモ科)、ケダニ亜目の一種も樹上に設置した網袋から見つかりました。こうした虫たちは暖かい日などに雪上に現れることがこれまでの調査で分かっています。こうした稀に現れる雪虫は樹木の幹を通り道として暖かい日に雪上に出現するのかもしれません。
今回の調査は2本の樹木だけで調査した簡単な実験でしたので、環境や時期を変えればまた異なる結果となるかもしれません。特に今回の調査ではクロユキノミがどういったルートで雪上に現れるのかは結局不明のままでした。今年度の雪虫しらべは今回で最後となりますので、今回の調査で得られた課題は来年度の雪虫しらべで改めて調査したいと思います。
今年度の雪虫しらべにご参加いただいた皆様に改めて感謝いたします。